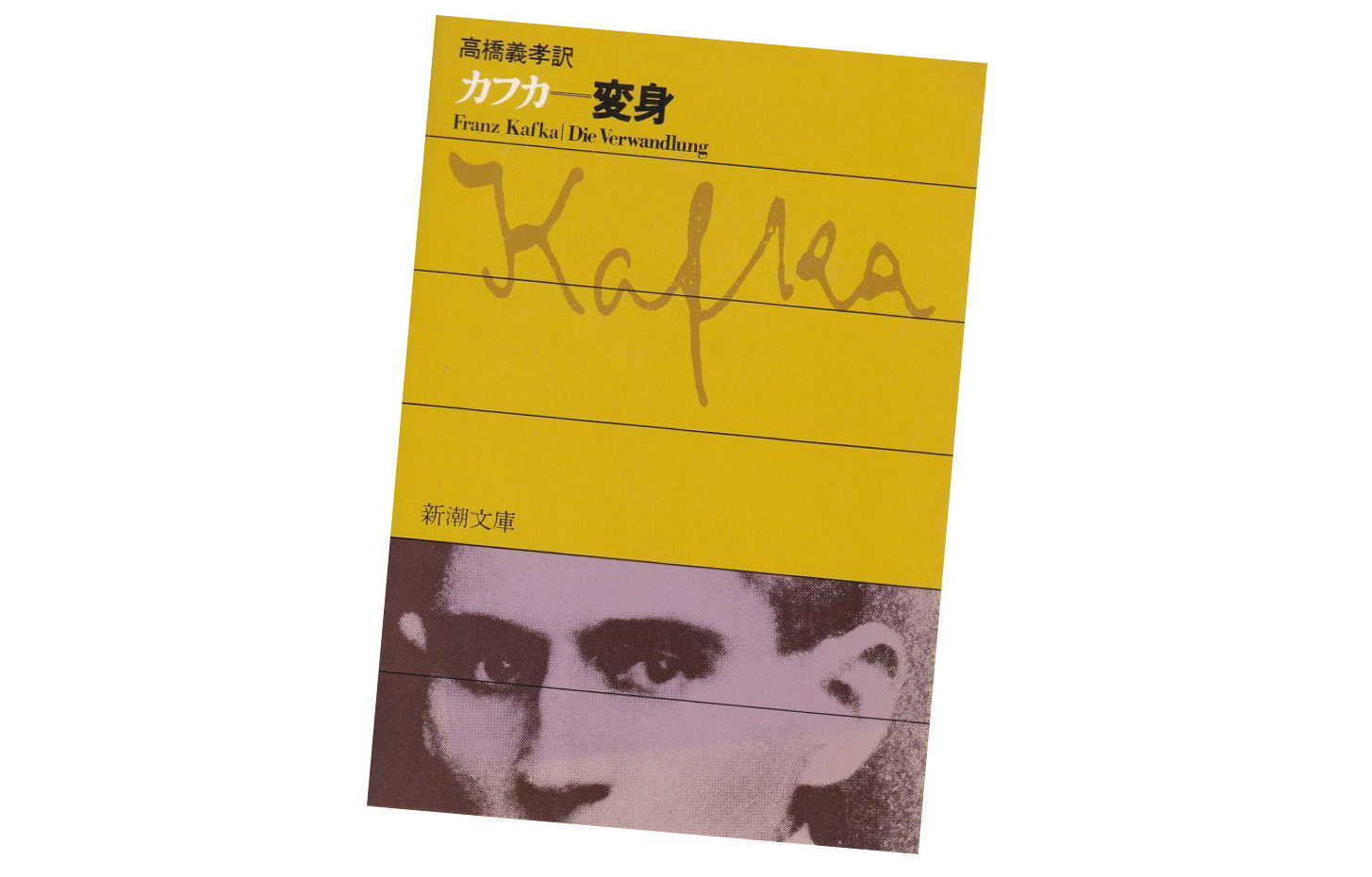高校2年のときの私は、とにかく苦しかった。理由は、自分にとうてい手の届かない目標を掲げていたからだ。
小学生のときに読んだパスツールの伝記の影響で、私は将来、研究医になりたいと思っていた。研究医になって新しい治療法を発見すれば、世界中の多くの患者を救える。同時に医学史にも名を刻むことができる。そのためには、まず医者にならなければならない。しかし、当時の私は、どれほど頑張っても、志望する大学の医学部に合格する成績を取ることができなかった。
私の通っていた高校は、戦前の旧制中学で、父も祖父もそこを卒業し、ともに地元の医学部に合格していた。私も負けるわけにはいかない。
そう思って、はじめはクラブと勉強の両立を目指したが、やがて無理だとあきらめ、勉強のみに絞って、昼夜を分かたず努力した。ノイローゼになりかけるほどだったが、成績は伸びなかった。そんなとき、苦しさのあまり、ふと私の胸にある疑問がよぎった。
この努力は、正しい方向に向かっているのか?
いくら苦しくても、正しいのであれば努力は惜しまない。しかし、もしも努力の結果得られたものが、何の価値もないものだったら、すべては無駄ではないか。
私は苦しみを乗り越えるために、だれが何と言おうと揺るがない真実を見つけたいと思っていた。
それとは別に、17歳の私を悩ませていたのは、どうして人間は悪いことをするのかという疑問だった。なぜ、人は善いことだけをしないのか。悪いとわかっていて悪いことをする人間の心理は何なのか。
父親に訊ねると、「人にはいろいろ都合や解釈があるから、悪いことをする者もいるのや」と、言われた。もちろん、納得はできない。
そのころ、イスラエルのテルアビブで、日本赤軍による乱射事件が起こった。罪のない人々が無差別に殺され、3人の犯人のうち2人がその場で自殺し、1人が死に損ねて逮捕された。私には衝撃だった。金銭目的でも、個人的な恨みでもなく、どうして無差別殺人が行えるのか。
何より私を驚かせたのは、テロリストたちが、貴重なはずの自分の命さえも顧みなかったことだ。彼らは自分の行いを“正しいこと”と信じてやったにちがいない。そうでなければ、辻褄が合わない。
当然、被害者からすれば、いや、世界中のだれにとっても、無差別テロは許しがたいに決まっている。ところが、テロリストおよびその背後にいる人々には、正しいことと認識されているのだ。
さらには同じ年、ミュンヘンオリピックの選手村でもテロがあった。平和の祭典、世界中がスポーツを通してひとつになろうとしているときに、それを踏みにじろうとする者がいる。もちろん私利私欲のためではない。テロリストたちはそれが正しい行為だと信じてやっているのだ。
いったい、この世の善と悪はどうなっているのか。
そのとき浮かんだのが、Aの晴天嫌いだった。多くの人が晴天を「いい天気」と言い、雨天を「天気が悪い」と言う。Aとは真逆の感覚だ。私も晴れを「いい天気」とは思えず、どちらかと言えば不快だった。多くの人は、晴れが自分にとって好ましい、都合がいいから「いい天気」と言うのであって、絶対的な評価ではない。すなわち、善悪の判断は恣意的なものということだ。
その根源にあるものは何か。
イワンのセリフが思い出される。
「神が存在しなければ、すべての行為は許される」
個々人の恣意は、どこまでも容認されるということか。しかし、いくら数が多くても、所詮、それは人間の領域に留まるものだ。
さらには、当時の私が立派なことと信じていた禁欲主義への疑問も浮かんだ。見たいテレビを我慢し、読みたい漫画を我慢し、眠たいのを我慢して、成績を上げるために勉強に取り組む。欲望や誘惑に負けない強い意志を持つことが、私には偉いことに思えていた。
しかし、それはつらいことだ。つらいから自分はなぜ禁欲するのかを考える。禁欲はほんとうに立派なことなのか。禁欲すればどんないいことがあるのか。しっかり勉強ができて、成績が上がる。そうすれば、大学受験に有利になる。結局、自分はいい大学に入りたいために、禁欲しているのか。真に禁欲主義を貫くなら、いい大学に入りたいという欲も、禁じるべきではないのか。
自己矛盾に陥った。だが、解はすぐに浮かんだ。簡単なことだ。禁欲は、単に禁欲したいという欲 に負けているにすぎない。
そう閃いた瞬間、世界が一変した。
あらゆる行為、善も悪も理想も堕落も、すべての原動力は人間の欲にほかならない。その一点において、何ら絶対的な差異はない。あるのは自分の都合による恣意的判断だけだ。テロもオリンピックも戦争も平和も、善行も悪行も禁欲も放蕩も、個人的な利害はあっても、絶対的な評価では等しい。
この考えは私の確信=ドグマになった。すべてがクリアになり、何が起ころうとも揺るがない確信を手に入れた気がした。私は自由になり、勉強するのもサボるのも、親孝行も親不孝も、規則を守るのも破るのも、人を信じるのも裏切るのも、何ら差がないと確信できるようになった。
後に、Aはこの考えを“Kの欲の一元論”と評した。私はこれでAに嫉妬も劣等感も羨望も抱くことがなくなった。いくらAが他人を露骨に軽蔑し、怒りを露わにし、弱い者を踏みにじるのに躊躇しなくても、それを畏敬することはなくなった。
私は、晴れてAの側の人間になったのである。
(つづく)