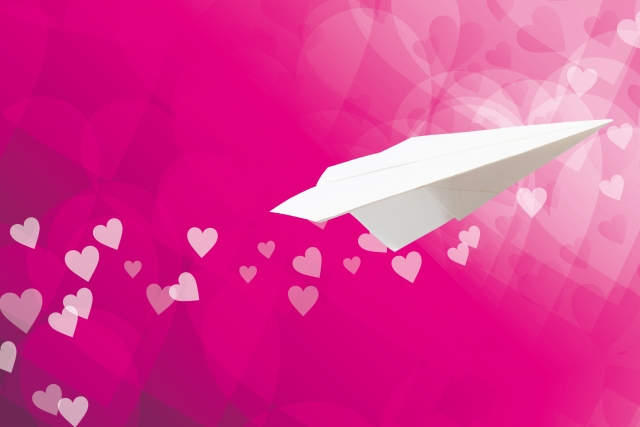高校3年の1学期、私はAとは別のクラスになり、教室で彼の視線を気にする必要もなくなった。そして、2年下のエッちゃんからつき合いOKの返事をもらい、いとも簡単に幸福の頂点に昇り詰めた。
はじめてのデートは、悩んだ末、映画に行くことにした。何を観るか。ありきたりな作品ではつまらない。1カ月以上も前から映画雑誌を読み漁り、初デートにぴったりの作品を見つけた。
『探偵』
ジャック・レモンとウォルター・マッソー主演の映画で、セリフのない無言劇らしかった。ユニークで、しかも喜劇の要素もある。きっと楽しい雰囲気になるだろう。私はさっそく前売り券を2枚買い、デート用に新しいトレーナーも買って、その日に備えた。
当日、難波駅の改札で待っていると、ミニのワンピースを着た彼女が来た。一瞬、めまいがしそうなほどカワイかった。これが自分の彼女かと思うと、まさに天にも昇る心地だった。
どぎまぎしながら階段で一階に下り、髙島屋の向かいにある映画館に行った。当時は指定席がなかったので、うまく並んで座れるかどうかが問題だったが、私はどんなことがあっても2席を確保する意気込みで入場口に進んだ。
ところが、そのときふと不吉な違和感がよぎった。映画館の前に出ている看板が、『探偵』ではなかったのだ。おかしい。もぎりの女性に前売り券を出すと、こう言われた。
「『探偵』はもう終わりましたよ」
ピンチという言葉はこういうときに使うのだろう。私はいったん通りにもどり、上映中の看板を見上げた。『ソイレント・グリーン』という作品で、チャールトン・ヘストンが必死の形相で何やらパニクっていた。
困ったけれど、映画を観るという予定が狂うと、あとの段取りも狂ってしまう。仕方なく上映中の映画を観ることにして、新たにチケットを買って中に入った。すでに本編がはじまっていて、空席も見当たらず、エッちゃんと私は客席の後ろに立って観なければならなかった。
これだけでもつらいのに、映画の内容は、近未来に人口が増えすぎて、食糧危機を脱するために開発された「ソイレント・グリーン」なる食べ物の原料が、実は人肉だったというホラーSFだった。これ以上、初デートに似つかわしくない映画があるだろうか。
映画を見終わったあと、楽しく感想を語り合うどころではなく、イヤなことは早く忘れたい気分だった。映画のあとは喫茶店に行くつもりだったので、戎橋筋のほうに向かって歩きだした。前もっておしゃれな喫茶店は下調べしてある。しかし、直行するのも照れ臭いので、軽い冗談のつもりで聞いてみた。
「もう帰る?」
恥ずかしそうに首を振るだろうと思っていたのに、彼女の返事は「ウン」。即答だった。
今のは冗談とも言い出せず、私は顔を引きつらせたまま駅に向かわざるを得なかった。しかも、彼女とは別々の路線のため、難波駅で別れなければならない。なんとかきっかけをつかんで、別れずにいたいと思ったが、無情にもホームにはすぐに発車する電車が待機していた。
かくして最初のデートは惨敗に終わった。経験不足の高校生には、些細な行きちがいも大失態のように思え、1週間ほどは立ち直ることができなかった。
次に私を悩ませたのは誕生日だった。
誕生日にプレゼントを渡すのは、高校生カップルにははずすことのできないイベントである。6月のある日、私は電話でエッちゃんに誕生日がいつかと訊ねた。まさか4月か5月で、もう終わっていたらどうしようとハラハラしながら訊ねると、幸い8月で、まだ余裕があった。逆に私は7月生まれなので、彼女が聞くタイミングを逸すると過ぎてしまう。かと言って、聞かれもしないのに自分から言うわけにもいかない。だが、これも幸い、私が訊ねたあとで、彼女のほうから「Kさんは?」と聞いてくれたので、首尾よく答えることができた。
7月のその日、通常の授業がある日だったので、私は朝から気が気ではなかった。極端な恥ずかしがりやの彼女が、校内でプレゼントを手渡したりできるだろうか。もしプレゼントがなかったら、この恋は終わりと覚悟せねばならない。そんな悲壮な気持で、当日は朝から授業にまったく集中できなかった。
昼休み、出会うチャンスが見込める学食で待ったが、彼女は現れなかった。午後の授業がはじまり、刻一刻と下校時刻が迫るなか、6時間目がはじまる直前、彼女が私の元カノの妹に付き添われて、3年生の教室にやってきた。そして、小さな包みを差し出した。
「あの、これ」
彼女が言えたのはそれだけだった。
「ありがとう」
私もそうとしか返せなかった。喜びと安堵で、口の中がカラカラだった。
家に帰って包みを開くと、手のひらに乗りそうな目覚まし時計が出てきた。エンジ色で、小さなベルに金の鎖がついている。私はそれをひねくりまわし、飽きずに眺めて、夢のような幸せにひたった。電話で礼を言ったが、何を話したかまるで覚えていない。ただ、それまでの人生で、いちばん幸福な日だったことにはまちがいない。
(つづく)