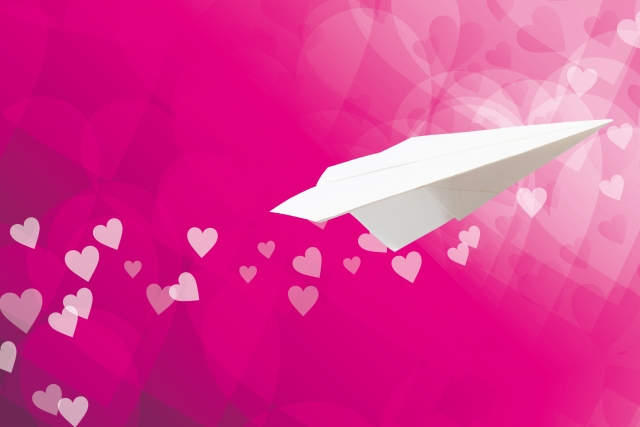奇矯なマントを羽織り、模擬試験で名前が張り出され、小説家になるという秘かな志も得て、私は高校2年3学期、自分の可能性に酔っていた。そういうとき、人は自らの危険な兆しに、気がつきにくいのかもしれない。
あとから思えば、その兆候はすでに明らかだった。3学期の定期試験で、修学旅行中に親しくなった優等生が、私の答案を見て心配そうにこう言った。
「おまえ、どうしたんや」
私には何のことかわからなかった。当時、定期試験の答案は、テスト終了後、各列の最後尾の生徒が集めて先生に提出することになっていた。最後尾の優等生は、答案を集めるたびに、私の答えをチラ見していたようだ。
彼の心配の理由はすぐに知れた。返ってきたテストが、どれもひどい出来だったのだ。2学期に満点を取った数学でさえ、信じられないほどの点数だった。
さらに深刻だったのは、私自身、それを予期していなかったことだ。テストはできたと思っていた。にもかかわらず、予想をはるかに下まわる点数だった。不愉快だったので、私は無視した。たまたまそうなっただけだ、気にすることはないと。
無視してしまえば、当面の不安も消える。慢心も維持できる。今から思うと、そんな危険なことはないが、浅はかな17歳の私は、現実を見ることから逃げていた。
そのまま春休みに入り、春の陽気とともに私に変化が訪れた。芸術と哲学を愛し、孤高を目指して俗物を軽蔑していたはずの私が、俄かに彼女がほしくなったのだ。それは発情としか思えない。修学旅行のとき、あれほど女子を好きになることを軽蔑したのに、このときはどうしても彼女がほしくてたまらなくなった。
4月1日、クラブの練習が終わったあと、私は仲のよかった部員と2人で、新入生の入学式を見にいった。かわいい子がいないかさがすためだ。同じ学年の女子とつき合うのは論外だった。そんなものは子どものじゃれ合いで、いかにも通俗的だ。こちらは3年生で、1年生の女の子とつき合う。これこそが高校生のロマンだと、根拠もなく決めつけていた。
新入生をチェックしていると、真新しい制服を着たモンチッチや土偶みたいな女子の中に、ひときわ輝いて見える子がいた。小柄でショートカット。遠目にもつぶらな瞳と長い睫毛が瞬いていた。しかも、1人だけ黒いソックスをはいている。私は一目惚れをして、その子のクラスを覚え、名前順に並んでいる番号を懸命に数えて、新学期に配られる全校生徒名簿を見て、彼女の名前を知った。
──ハタバ・エツコ
そのころ私はチェリッシュの松井悦子のファンだった。エッちゃん。同じ名前だ。運命を感じた。しかも彼女は、2年前に私を振った元カノの妹と同じクラスだった。その伝手を使わない手はない。私は久しぶりに元カノに電話をして、好きな子ができた、おまえの妹と同じクラスの子だから、手紙を渡してほしいと頼んだ。
元カノは快く引き受けてくれた。が、恋文など書いたことがない。私はあらんかぎりの知恵を絞り、推敲に推敲を重ねて文面を考えた。自分の情熱の激しさを伝え、かと言ってあまり押しつけがましくなく、つき合うのがいやならNOと答えやすいように配慮し、それでもできるだけYESと答えてもらえるように、少しは自分の魅力も伝え、でも自慢にならないように、相手を萎縮させないように(なにしろ向こうは新入生なのだ)、簡潔に、丁寧に、さわやかに、かつ真面目に感じてもらえるように練りに練った文面は、今考えると、思わず自分に往復ビンタを食らわせたくなるようなものだった。
──見も知らぬ者からの手紙で、さぞかし驚いたことと思います。
そんな書き出しだったと思う。そのあと自己紹介をして、こんなことを書いた。
──霧の立ち込める森の小径を、君と二人、小さな馬車に乗って、どこまでも行けたらどれほどいいだろう。
恥ずかしぎる。
堕落したとはいえ、当時の私は恋愛にもいびつな文学趣味があったため、イメージは『初恋』のアレクサンダーとズィナイーダや、『罪と罰』のラスコーリニコフとソーニャのような関係だった。そんな手紙をもらった彼女は、さぞかし困惑したことだろう。
それから1週間ほどして、元カノ経由で返事が届いた。封筒の薄さから、便せんは1枚だと予測された。YESかNOか。私はかつてないほど緊張して封を切った。
折りたたまれた便せんに透ける文面は、ほんの1行だった。やはりNOなのか。崖から突き落とされそうな気分で便せんを開くと、次の一文が書いてあった。
──わたしの他愛ない話を、聞いてもらえたら嬉しいです。
天にも昇る心地とはこのことだろう。私はその薄い紙を持ったまま、しばし、恍惚の人となった。
(つづく)