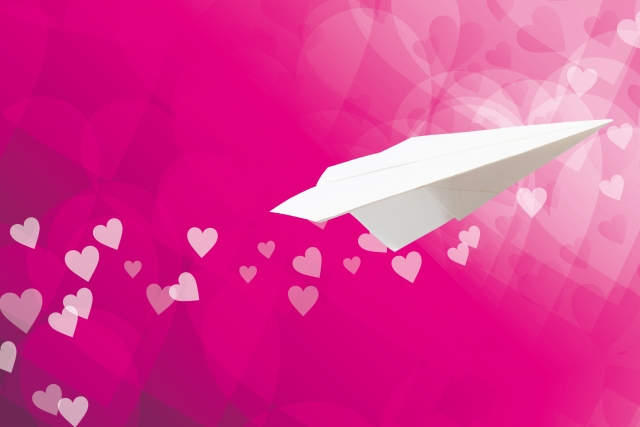高校2年の冬、私はとにかく個性的でありたいと願っていた。
もともと、人と同じというのがいやな性格だったので、団体行動も苦手だったし、みんなで何かを成し遂げるというようなことも嫌いだった。祭りや盆踊りの雰囲気は好きだったが、あくまでその中でも自由でいたかった。そういう意味で、規律や常識に従わないAは、強烈に個性的に思えた。今でいう“空気を読む”などということは、当時のAにはあり得なかった。
そんな強いAに対して、内面で劣る私は、外見の虚飾で対抗するしかなかった。
12月の声を聞いて、そろそろ学生服だけでは寒くなりかけたとき、祖母が私にこんなことを言った。
──おじいちゃんが学生時代に着てたマントが、奥にあると思うで。
私は祖母に頼んで、そのマントを出してもらった。分厚い羅紗地のマントで、色は抹茶羊羹色、襟のところにホックと留め紐がついていた。羽織ってみると、『金色夜叉』の間寛一になったような気分だった。
大いに気に入り、さっそく翌日から羽織って登校することにした。マントを着るだけでは物足りず、伸び放題だった蓬髪に父親のチックを塗り、耳の両側に逆立てた。ベートーヴェンの伝記に出ていた肖像画から思いついたものだが、手塚治虫の漫画に出てくる「魔人ガロン」もイメージした。ビジュアル系はおろか、パンクロッカーさえ周知されていないころだから、かなり異質だったはずだ。
私は個性的であることと、単に変人であることを混同していたのだ。
その姿に有頂天になり、マントで登校する初日はわざと遅刻して、人気のない校門を通り抜け、クラスの全員が授業を受けているところに堂々と登場した。1時間目は、仇敵タルイの数学だった。タルイは私の奇矯な姿を見て、一瞬、唖然としたが、無視するのが得策と考えたのか、咳払いひとつで授業を継続した。
級友の反応はさまざまだった。驚く者、笑う者、舌打ちをする者、気味悪がる者。私は当然、そのすべてを無視して、超然と自分の席に着いた。
Aはそんな私を見て、軽侮するような苦笑を浮かべた。むろん、私はそれに対して、何の反応も見せなかった。それが“コム・イル・フォー”の流儀だと思ったからだ。
帰宅後、私は日記に自分の絵姿を描いて悦に入った。日記は今も残っているが、吹き出しにはこんなセリフが書いてある。
『これこそオレのあこがれていたスタイルダ イヒヒヒヒ…… ざまぁみやがれ』
水木しげるの『劇画ヒットラー』で、浮浪者収容所にいた若きヒットラーが、芸術的画家を気取って、ユダヤ人からもらったカフタンコートを着てうそぶくセリフだ。
土曜日にクリサキケイコという女子が、私にマントを貸してくれと言ってきた。クリサキは、模試の成績が450人中449番で、「まだ、わたしより下の人がいるわー」と公言するような天真爛漫な女子だった。ショートカットで目も髪も栗色で、仕草も言葉も無邪気な幼女のようだった。私は彼女と親しいわけではなかったが、Aが1年生のときに同じクラスだったことから、私に近づいてきたらしい。
「わたし、いっぺんそんなマントを着てみたかってん。そやから貸して。お願い」
ベートーヴェン・ヘアスタイルでしかめ面の私は、クリサキにあっけらかんと手を合わされて、毒気を抜かれてしまった。
「月曜日には返すからね」
マントを羽織ったクリサキは、スキップしながら帰って行った。
見ていたAが、愉快そうに笑った。
「クリサキのことやから、マントが返ってきたら、アップリケかなんかついてるかもしれんぞ」
たしかにその可能性はあり、私は不安になったが、幸い、月曜日にもどってきたマントは無事だった。
しばらくすると、別の高校に通う中学時代の同級生が、私に電話をかけてきて言った。
「おまえの高校に、勉強のしすぎで頭がおかしなって、マントを着てるヤツがおるらしいな」
それ、オレやがな。そう思ったが、苦笑いでごまかした。
後年、高校の同窓会に出席しても、「ああ、マントのK君」と呼ばれたり、伝説のようなことを言われたりした。
──K君、マントのときは高下駄もはいてたよね。
──黄金バットみたいに笑いながら、マントを広げて走ってたでしょ。
──駅のホームにバッと飛び上がってきたとき、マントに虫食いの穴が開いてたの、見えたよ。
高校3年の冬はトレンチコートを着たので、マントを着用したのは、高校2年のほんの3カ月ほどだった。にもかかわらず、この奇異な出で立ちは、多くの人間に強い印象を与えたようだった。
(つづく)