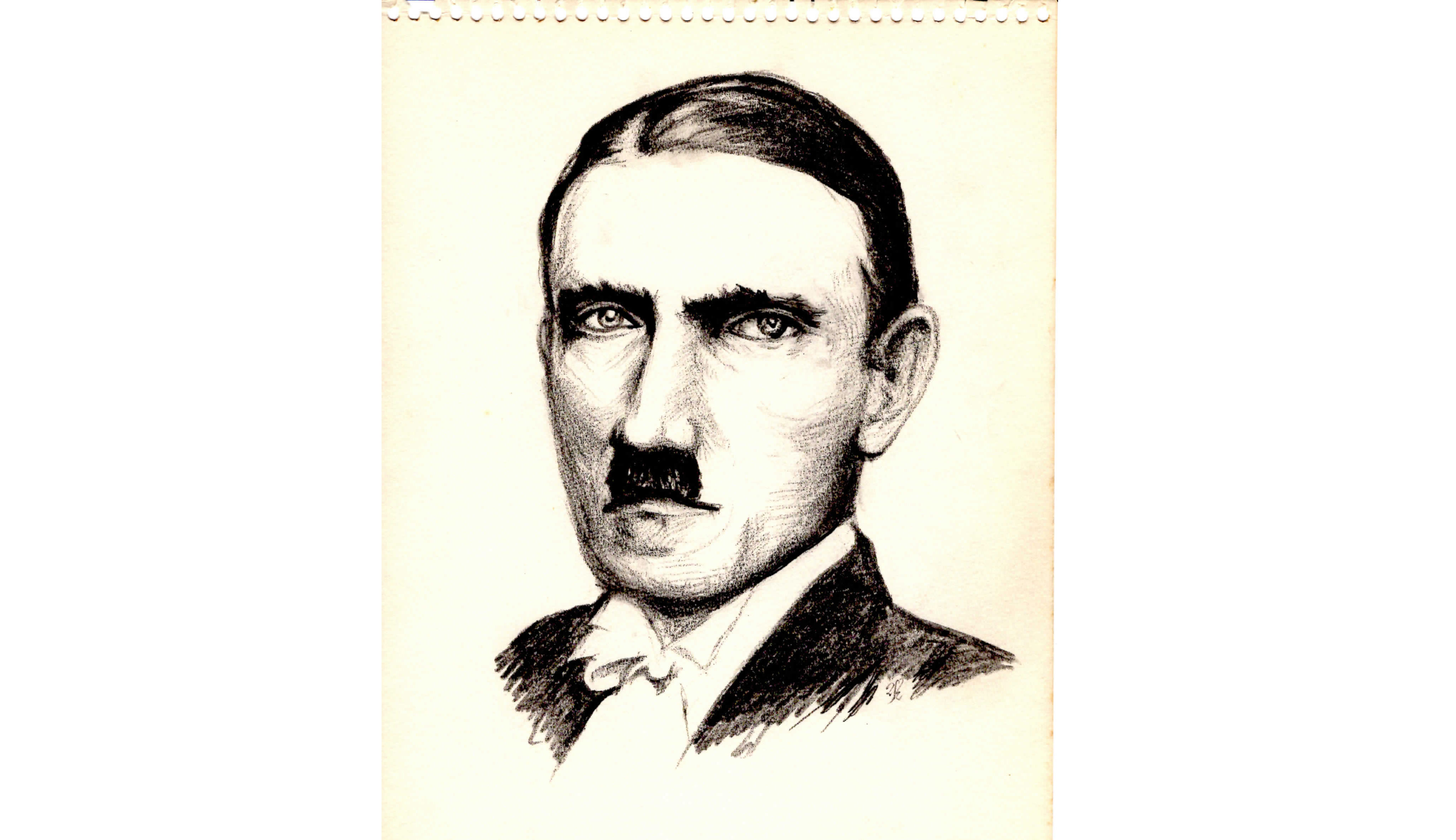“Comme il faut”(コム・イル・フォー)とは、“品のよい”とか、“礼儀をわきまえた”とかいう意味のフランス語である。この言葉はトルストイの『青年時代』に出てくる。
この概念が、17歳のAをいたく魅了し、彼の価値判断の絶対基準のようになっていた。
そもそも、Aが高校1年の1学期にクラスでトップの成績を取りながら、勉強に興味を失ったきっかけが、トルストイの『戦争と平和』だったのだから、彼にとってトルストイが特別な存在だったのはうなずける。
Aは熱意を込めて私に語った。
「16歳のトルストイは、すべての人間を“コム・イル・フォー”と、そうでない者に分類していたんや。“コム・イル・フォー”でない人間は“ヴァルガー”、すなわち“俗物”として軽蔑していた」
その分類は、彼自身が同級生や教師に対して行っていたものに近かったのかもしれない。
「“コム・イル・フォー”の条件は、まず爪の美しさや。よく磨かれた長くて清潔な爪。トルストイには何人か兄がいて、どの兄も完璧な“コム・イル・フォー”やったから、トルストイも同じようになりたいと、涙ぐましい努力をした。しかし、いくらきれいに爪を磨いても、美しく調えることができない。そこで兄の1人に、どうやったらそんなきれいな爪になるのか訊ねた。すると兄は、今まで爪のことなど気にかけたこともないし、ちゃんとした人間がこれとちがう爪でいる理由がわからないと答えて、トルストイを失望させるんや」
Aは顔や服装といった一般的に注目されるところでなく、爪という細部に着目したトルストイに心酔したのだろう。さらには、懸命に“コム・イル・フォー”たらんと励んでいるトルストイの傍らで、兄たちが何の努力もせずに、やすやすとその資質を手に入れていることに、哀しい皮肉を見たのかもしれない。
ほかにもトルストイの惨めな失敗を、Aは親愛を込めて語った。
「トルストイの兄たちは眉毛が濃くて、それに憧れたトルストイは、自分の眉も濃く見せようとして、ローソクの火で焦がしたりもしてるんや。かわいそうなくらい滑稽やろ。“コム・イル・フォー”の要件である優雅なお辞儀や、流暢なフランス語、ダンスの才や機知に富んだ会話も、すべてトルストイは兄たちに劣っていた。兄たちは貴族の子弟として、すべての要件をごく自然に身につけていたんや」
Aは持って生まれた才能や資質に敬意を払いながらも、それが得てして意識的な人間にではなく、深い考えのない人間に与えられる矛盾に、マゾヒティックな納得を感じていたのかもしれない。
ほかにも、Aは“コム・イル・フォー”の要件として、筆跡とか手袋とか、ズボンと靴の関係なども忘れてはならないと言っていたが、もっとも重要なのは、あらゆることへの無関心だと強調した。
「“コム・イル・フォー”であるためには、ある種の洗練された倦怠の表情と、あらゆるものに対する無関心が必要なんや。何かに一生懸命になるとか、おもしろがったり、興味を示すのは“ヴァルガー”のすることやからな。それで“コム・イル・フォー”にとって最大の屈辱は、“コム・イル・フォー”たらんと努力していることを、他人に知られることや」
それは彼がかつて言っていたこと──才能は浪費することに意味がある──にも通じる、ある種の高踏的なニヒリズムだったろう。
Aは別に私を揶揄するために“コム・イル・フォー”を讃美したのではなかったと思う。そんな素振りは一度も見られなかった。当時、私はまだ勉強に価値を見出しており、Aの超然とした態度に憧れながらも、Aの側に舵を切れずにいた。私は“コム・イル・フォー”に惹かれながら、“ヴァルガー”であり続けるというアンビヴァレントな状況に、引き裂かれそうになっていたのだ。
それは私にはたいへん苦しい状況だった。
(つづく)