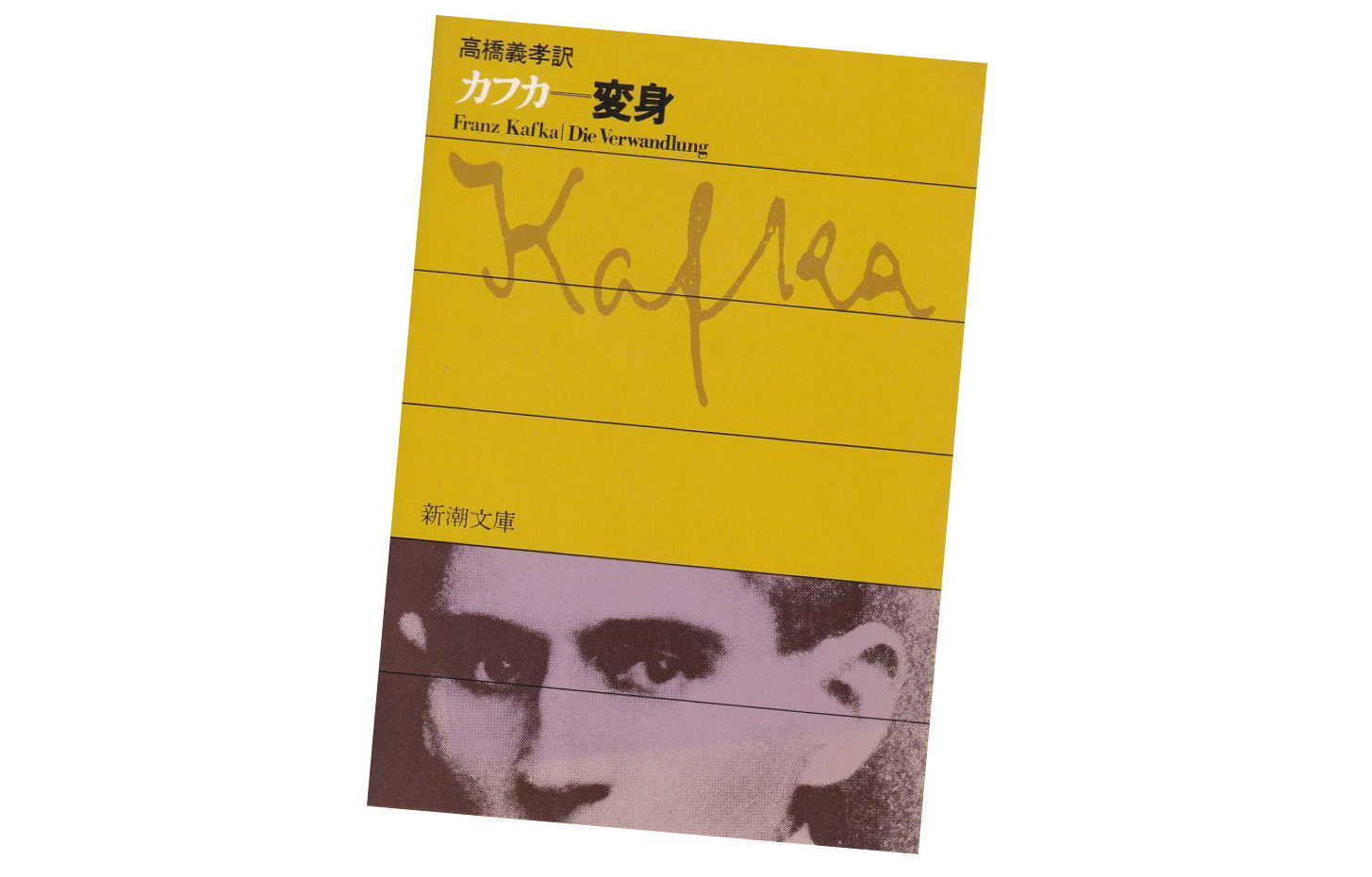『地下室の手記』で、Aが特に好んだエピソードに、地下室の住人と将校との対決がある。
地下室の住人が撞球場に行って、撞球台の横でぼんやり立っていると、前から来た将校が彼の両肩をつかみ、まるで邪魔な荷物か何かのように、横にすげかえるという場面だ。地下室の住人は、その扱いに深い屈辱を感じて激怒する。将校が人間に対する最低限の敬意も払わず、自分を完全にモノ扱いしたからだ。
将校は地位も、外見も、豊かさも、地下室の住人よりはるかに優っていたため、地下室の住人は何の抵抗もできずに終わる。そのまま地下室に帰るが、怒りは収まらず、高慢であらゆる面で恵まれた将校に、いつか復讐をしてやると心に誓う。そして、復讐の日に備えて、体面を保つために、わざわざ外套の襟をビーバーの毛皮に取り替えたりする。
その後、偶然、大通りでその将校が前から歩いてくるのを見つけたとき、地下室の住人は1歩たりとも道を譲らず、その場に立ち尽くして、すれちがいざま将校と肩が触れ合う。そのことで、地下室の住人は自分と将校が対等であることを自らに証明し、復讐の成就を実感するのである。
ふつうに考えれば、なんとせせこましい心理かと思えるかもしれない。だが、Aはこのエピソードに深く共感していた。この心理をせせこましいとか、みみっちいとかしか受け取れないのは、その人間が件の将校と同じく、粗雑な感性しか持ち得ていないからだ。Aはそう思っていたにちがいない。
Aにとって、この将校は、恵まれた環境で社会的にも人生的にも成功しているやり手のヴァルガー(俗物)の象徴だったのだろう。現実社会では、精神的〝コム・イル・フォー〟である地下室の住人は、前向きなヴァルガーに確実に敗北する。なぜなら、地下室の住人は、何かをするにはあまりに思索的すぎるからだ。その不条理に、おそらくAは、いかんともしがたい虚無と冷笑を感じていたのだろう。その心情は私にもよくわかる。
私もこのエピソードに興奮し、さっそく『地下室の手記』を読みはじめた。しかし、難解すぎて、少しも内容が頭に入ってこなかった。Aが語った将校との対決の場面さえ、おもしろいとは思えなかった。私が興奮したのは、まさにAの語り口のうまさだったのだ。彼の口を通すと、人物が生き、セリフが現実味を帯び、状況の異様さが際立つのだった。
似たようなことは、『カラマーゾフの兄弟』でもあった。
Aがもっとも気に入っていたのは、カラマーゾフ家の料理人で、フョードルの私生児の噂があるスメルジャコフだった。
「スメルジャコフは異様なほど潔癖で、スープを飲む前には、スプーンですくって光にかざすし、服には1日に2度もブラシをかけて入念に手入れをし、英国製の靴はワックスでいつもピカピカに磨いてあるんや。常に薄笑いを浮かべて、部屋の隅から家人のようすを横目でうかがったりする。それで、子どものころの遊びは、子猫を縛り首にして、葬式ごっこをすることやった」
そう聞くと、私にはスメルジャコフがまるで実在の人物のように思われ、その独特の異様さがたまらなく魅力的に感じられた。
絵のうまいAは、ノートにスメルジャコフの絵も描いていた。フロックコートを着て、ピカピカの靴を履き、異様な笑みを浮かべながら、身体を前に倒して人差し指を突き出している。その顔はA自身にそっくりだった。
以前、銀縁眼鏡をかけた凜とした自画像を描いて、級友に見られて屈辱にまみれたAは、今度は極端に卑しい異常人格者に自分をなぞらえたのだ。
Aはスメルジャコフ以外にも、次兄のイワンにも惹かれていた。
「イワンは父親のフョードルにこう言うんや。神が存在しなければ、すべての行為は許される、とな」
Aが言うと、私はイワン・カラマーゾフその人に、この鮮烈なテーゼを突きつけられたような気がして、激しく動揺した。神が存在するか否かの議論は、私の中ではソクラテス以来の不可知論で止まっており、それ以上の深淵には踏み込んでいなかった。イワンのテーゼが正しければ、神が存在しない場合、差別も虐待も裏切りも盗みも殺人も戦争も、すべて許されることになる。なんとなく、神なんかおらんやろうと感じていた私が、動揺するのも当然だろう。
〝コム・イル・フォー〟や地下室の住人、スメルジャコフやイワンらの思想は、Aのよりどころだった。Aの側に立って眺めると、級友たちはいずれも即物的で、軽薄で、浅はかで、無思慮だった。
級友たちの側から見れば、Aはただのドロップアウトした変わり者でしかなかっただろう。しかし、私には、Aはだれよりも先鋭で思慮深く魅力的に思われた。そして、彼の特異性と優秀さを理解しているのは自分だけだという自覚が、密かな優越感をもたらしてもいた。
(つづく)