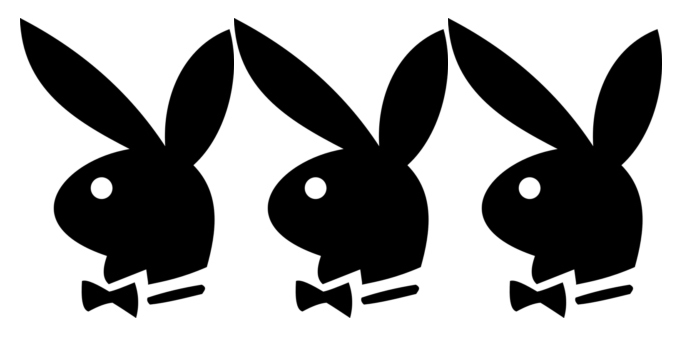大学教養部の2年間、私は苦しかった予備校時代の反動で、羽を伸ばすことに専念した。
車の免許を取り、親に中古のフォルクスワーゲンを買ってもらい、サッカーに打ち込み、一人旅に出たり、映画を観まくったり、当時、コンポと呼ばれたステレオセットを買って、さまざまな音楽を聴いたり、級友たちとスキーツアーに参加したりと、多忙な毎日を送った。ファッションに凝って、10センチほどの厚底サンダルを履いたり、わざと女性用のブラウスを着たり、プルオーバーに油絵具でマルキ・ド・サドやゴッホの肖像画を描いて着たりもした。奇抜なことが好きな私には、まさに自由気まま、やりたい放題の時間だった。
教養部の講義は、憲法や統計学、熱力学など、興味のないものばかりだったので、ほとんど講義には出ず、出てもノートの類いはいっさい採らず、試験はすべてクキタをはじめとする優秀な友だちに頼んで、カンニングで単位をもらった。今なら大問題だが、当時はそんな些細なことに目くじらを立てる風潮もなく、教授も見て見ぬふりだった。
高校時代に苦悩のタネだったエッチャンとの恋愛は、私が大学に合格した年、彼女が高校3年生で受験生となったため進展することはなく、1年待っていよいよ本格的に付き合えると思ったら、今度は彼女が浪人することになり、なかなか思うように会えないまま、自然消滅してしまった。
代わりに遊び好きの仲間といると、女子大生と知り合う機会も増え、デートらしいことも何度かした。それはそれで楽しかったが、心はいっこうに満たされなかった。胸の奥に秘めた思い、小説家になるという志が、まったく実現に近づかなかったからだ。
遊びほうけていた日々の合間にも、私は小説の習作を書き続けた。講義に出る代わりに図書室で原稿を書いたり、キャンパスの端にある池の縁をひとり巡って、夢想にふけったりした。読んでは書き、書いては読む。まったくの我流で、湧き上がるイメージを文章にして、ひとつの作品に仕上げようとしたら、別の構想が浮かんで、猛烈な勢いで原稿用紙を埋めたりした。
しかし、そもそも、どうすれば小説家になれるのか。画家になるなら美大、音楽家になるなら音大、噺家になるなら師匠に弟子入り、プロ野球選手になるなら球団のテストを受けるなど、プロになる道筋はいろいろあるが、小説家になる方法がわからない。
3回生になって、無事に専門課程に進んだ私は、2年間、遊びほうけたのだから、今度は勉強に邁進しようと心を入れ替えた。ただ勉強するだけでなく、わからないことがあったら、アイツに聞けば何でもわかると言われるほどの存在になろうとさえ思った。
だから、4月から基礎医学の講義がはじまると、私は階段教室のほぼ最前列に陣取って、教授の言葉をひとことも聞き漏らすまいと集中し、あまつさえ自宅に帰ってからも、予習と復習を欠かさないようにした。予備校時代にもどったような勉強ぶりだったが、2年間のブランクは大きく、4月の末にはかなり疲れてしまった。が、うまい具合にゴールデンウィークに入ったので、講義を聴く苦しみから解放され、久しぶりに脳を休めることができた。
連休明けの初日、私はふたたび講義室の二列目あたりに座り、講義に集中しようとした。ところが、午後、生化学の講義を聴いていたとき、ふいに、こんなことをしていては小説家になれない! という思いが湧き上がった。居ても立ってもいられなくなり、講義が終わると、次の講義は無視して大学を飛び出し、最寄りの書店に直行した。小説家になるには文芸誌の新人賞に応募すればいいという考えが閃いたのだ。
文芸誌といっても、純文学と大衆文学のちがいもわからなかったので、取りあえず「中央公論」と「小説現代」を買った。どちらにも新人賞の募集があり、たまたま庄司薫が「中央公論」の新人賞を受賞してデビューしたというのを知っていたので、「中央公論」に応募することにした。締め切りは6月末で、残り2カ月もない。それでも私は憑かれたように書きはじめた。原稿用紙がなかったので、手近にあった大判のグラフ用紙を使って、それまでメモしていた夢の話を切り貼りして、シュールな幻想小説もどきを書いた。タイトルは「ソウル・バースデイ」。
これで受賞すれば一気に小説家デビューだ。そんなウマイ話があるわけはないと思いつつも、「恍惚と不安、ふたつ我にあり」の心境だった。
結果は、当然、落選で、一次予選も通過せず。しかし、以後、私はふたたび小説に没頭するようになり、講義や実習には必要最低限しか出席しなくなった。
あの1カ月の勉強熱は、一時の気の迷いだったのだろう。
(つづく)