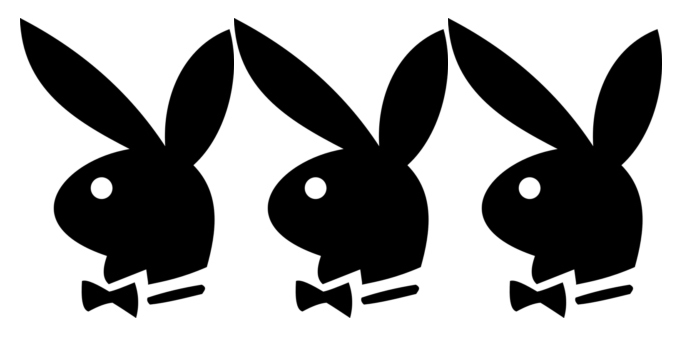文芸雑誌の新人賞に応募しても、一次選考にさえ通らないことに落胆して、私は文芸雑誌を軽蔑するようになった。商業主義におもねってどうする、自分の志はもっと高いはずだと、そんな気概だった。要するに、私はダメな人間がよく陥る似非孤高の穴ぐらに逃げ込んだのだ。
新人賞への応募をやめたあと、私はレポート用紙にびっしりと細かい字で、難解な思想小説を書きだした。タイトルは「Fの報告書」。Fはフランツ・カフカをイメージしたもので、雰囲気は安部公房の「S・カルマ氏の犯罪」を参考にした。
青年Fがある夜、たまたま通りがかった家の庭から、ツトツトツトという気がかりな機械音を聞いて、扉の隙間からのぞくと、奇妙な現象を目撃する。その後、庭をのぞくたびにちがったものが見え、青年は次第に現実を疑うようになる。ストーリーの展開もなく、人間ドラマもなしに、ただ、ああでもないこうでもないと、思索を垂れ流すだけの作品だった。
それでも原稿用紙に換算して100枚ほどになったので、唐突にピリオドを打ち、Aの家に持って行った。唯一の理解者であるAに読んでもらうためだ。たまたまAは留守だったので、彼の母親に原稿を托した。
ひと月ほどして、Aはその作品を返してくれた。感想は手紙に書くとのことだったので、楽しみに待っていると、送られてきた手紙には、『庭の樹が風に揺れるときの「サワサワ」という音の描写がおもしろかった』くらいしか書かれておらず、私が力を込めたカフカ風の情景や、ドストエフスキーばりの難解な自問自答については何も触れていなかった。商業主義の文芸雑誌に無視されても平気だったが、頼みの綱のAもほぼ無反応だったことで、私は大いに落ち込んだ。
大学3回生の夏休みの終わりがけに、Aが京都の下宿に遊びに来ないかと私を誘った。そのとき彼は堺に帰っていたので、地元の駅からいっしょに京都に向かった。大学は京都市の北のはずれにあり、京都駅から30分ほどバスに揺られた。蒸し暑かったが、空はどんより曇っていて、2人の好みに合っていた。
夏休みの大学は人気がなく、古びた校舎がいっそうみすぼらしく見えた。Aは美術部に所属していて、部室兼アトリエを見せてくれた。小学校の教室くらいの広さで、部員の絵がいくつかイーゼルに載っていた。Aはその中の1枚の前に立ち止まり、「これはムロダタダスの絵や」と言った。ムロダは美術部で唯一、Aが一目置く部員で、富山の出身の同い年だった。
「ムロダの絵の特徴は、この微妙な色遣いなんや」
描かれていたのは、暗闇にうごめく光る霧のようなもので、色の境目がわからないように描かれていた。形がないので、私はムロダの絵がうまいのかヘタなのか、わからなかった。
Aの下宿に行くと、比較的新しい6畳1間だったが、あまりの乱雑さに驚かされた。床には本や食器や食材、服などが散らばり、足の踏み場もないほどで、冷蔵庫は開けっ放し、ベッドには真夏なのに冬布団がよじれていた。
辛うじてベッドの端に座ると、Aは輸入版の「PLAYBOY」を見せてくれた。当時、アメリカはポルノ解禁だったが、日本ではNGなので、局部に濃いマジックインキのようなものが塗られていた。Aはそれを取る苦心を語った。
「墨塗りのインクはシンナーやアルコールでは取れへん。溶かしたバターで拭うと取れると聞いたんやけど、何度もこすると色素が飛んで、肝心の部分がネガのように白黒反転してしまうんや」
ページを繰ると、たしかに墨は消えていたが、影絵のようにうっすらとしか見えない局部は、少しも官能的でなかった。
そのあと、自転車を借りて左京区の古い町並みを徘徊したり、宝ヶ池に放置されていたボート見つけて、板きれをオールの代わりに池の中央まで漕ぎ出したりした。
日が暮れたので、先ほどAがほめていたムロダタダスを訪ねることにした。ムロダの下宿は古い木造で、二階の彼の部屋は明かりが消えていた。留守かと思って見に行くと、ムロダは真っ暗な部屋で、パンツ一丁で料理をしていた。私は唖然としたが、本人によると、クーラーがないので窓を開けざるを得ず、明かりをつけると蚊や蛾が入ってくるので、部屋を暗くしているとのことだった。パンツ一丁なのも、暑いからのようだ。
食事の邪魔をしては悪いので、Aと私はスーパーへ食べ物とウイスキーを買いに行き、ころ合いを見計らって、ふたたびムロダの下宿にもどった。食事は終わっていたが、ムロダの部屋には水道がないので、食器はティッシュで拭いて、食器棚もないので、床に並べていた。
暗い中で3人でウイスキーを飲みながら、深夜2時半ごろまで語り明かした。Aが評価しているムロダとの会話だったので、期待したが内容はまるで覚えていない。酔っていても、印象に残る会話は覚えているので、このときはそれほどの話が出なかったのだろう。
考えれば、Aと酒を飲んだのは、このときがはじめてだった。大学の友人とはよく飲んだが、会話は刹那的なものばかりで、何の感興も湧かなかった。Aとならもっと深遠な話ができるだろうにと、何度も思ったものだ。
ところが、この夜は印象に残る話は何もなかった。残念ながら、ムロダとAに対する期待は、私の勝手な幻想だったようだ。
(つづく)