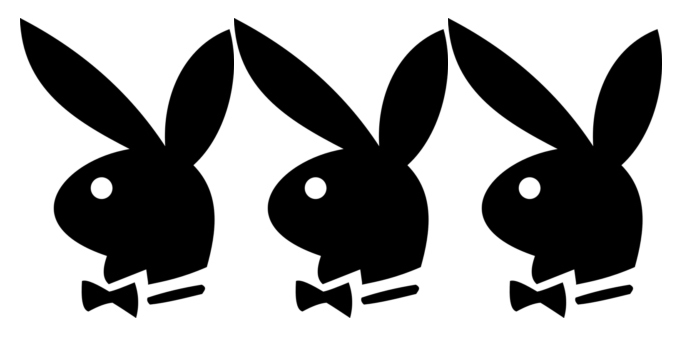京都でムロダの下宿を出たあと、Aと私は泥酔のまま、自転車で深夜の町をさまよった。そのとき、Aがこんな話をした。
「真冬に雪が降ったとき、雪見酒をしようと思って、外で日本酒を飲んでたら、寒うなって、身体を温めるためにしこたま飲んだら、急性アルコール中毒みたいになって、救急車で運ばれたんや。病院の廊下を通るときも、担架の上からボタボタ吐いたんやけど、自分ではどうにもならんかった。保険証を持ってなかったから、えらく高く取られたけど、家にも言われへんしな」
私はAがそんなふうに無軌道な行動の果てに、飢えた狼のように野垂れ死にをする場面を想像して、楽しそうに笑った。すると、彼は自嘲するようにこう続けた。
「人が破滅するところを見るのは、おもしろいやろうけどな」
私は自分の魂胆を見抜かれたように思い、ハッとした。
それからしばらくして、また飲みに行こうということになった。大学の友だちとはよく飲んでいたが、Aとは徘徊のような散歩をしながら話すのが常だったので、2人で飲むことには違和感があった。京都での一夜は別として、酒を飲むというヴァルガーな行為を、Aと共有することには抵抗があったのだ。
難波で待ち合わせて、私たちは地下鉄四つ橋線の近くにある串カツ屋に入った。矩形のカウンターだけの店で、ビールで乾杯したあと、私はいつも通り、小説や哲学の話をしようとした。
ところが、Aは何かの拍子に、ある集まりの二次会でカラオケに行き、『我が良き友よ』を歌ったと言った。私は、えっ、と声には出さなかったが、耳を疑った。私もカラオケは歌うが、それは仮の姿で、あくまで本来の自分ではない。だから、Aといるときにはぜったいにそんな話はしない。なのに、コム・イル・フォーの手本であるべきAが、ヴァルガーの象徴のようなカラオケのことを話したことが、私には耐えがたい裏切りのように思えた。
その串カツ屋には、棚の上にポータブルテレビが置いてあり、テレビ版の『犬神家の一族』を流していた。番組が終わりかけたとき、Aがテレビをじっと見はじめた。
「どうしたんや」と聞くと、「最後に流れる茶木みやこのテーマ曲がええんや」と言い、期待にあふれた目でテレビを見上げた。
ところが、店主がエンディングを待たずに、チャンネルを変えてしまった。Aは「ああっ」と、悲鳴のような声をあげ、「最後の曲が楽しみやから、今まで見てたのに」と嘆いた。
その一連の言動も、私には受け入れがたかった。テレビドラマのテーマ曲を楽しみにするなんて、Aはいったいどうなったのか。彼はすでに4回生で、来春に卒業を控え、就職という世知辛い現実に取り込まれてしまったのかもしれない。
店を出たあと、最寄りの駅までいっしょに帰ったが、何となく別れがたく、私はAを近くの雑木林に誘った。そこで私はAを遠まわしに批判した。Aの現実への対応は、堕落にも等しい。私は小説に覚醒しているので、表面上は現実に対応しているように見えても、内面は決して堕落していない。そんなことを話したと思う。
途中で、私は近くに転がっていた大きな石の上に乗った。すると、目の位置が30センチほど高くなり、Aを見下ろす形になった。実際、胸の内でAを見下していた。
いくら議論しても、私の視線は常にAを見下ろしている。Aもそれを意識したようで、次第に声が苛立ってきた。
そして、ついに我慢しきれなくなったのか、Aは横の楠の大木に取りつき、竹登りの要領でするすると上って、3メートルほどの高さにある太い枝にまたがった。それで私を見下げる位置についたが、私はわざとAを見上げなかった。目を伏せたまま、薄笑いさえ浮かべた。私に対抗するために、まるでサルのように木に登ったAの滑稽さを嗤ったのだ。
その状態でしばらくやり取りが続いたが、私は頑としてAの言い分に納得せず、執拗に持論を繰り返した。すると、突然、私のすべてを否定するような言葉が降ってきた。
「なんて頑固なんや」
怒りのこもった声でそう言い捨てると、Aは木から下り、そのまま荒々しく立ち去ってしまった。
私は今一度、Aがこちらを見るのではないかと思い、石の上に立ったまま冷笑を浮かべていた。しかし、彼はまったく振り返るそぶりもなく、暗い道の先に消えた。今度は私が滑稽な姿をさらす番だった。だれもいない深夜の雑木林で、ひとり石の上に立っている私。仕方なく、地面に下り、よろけながら家に帰った。
それがAと私の唐突な別れだった。
私はAに何を期待したのか。
私よりもはるかに優れた才能を持ち、卓越した理解力と鋭い批評眼を持つAに、私は常に刺激を受け、感心し、怖れてさえいた。私が哲学的な思考を身につけたのも、小説に目覚めたのも、すべてAのおかげだ。訣別の責任は私にある。
Aとすごした純粋な時間、交わした議論、教えられた概念や発想は、今も私に大きな影響を与えている。それはつい昨日のことのようでもあり、錯覚か幻のようでもある。曲がりなりにも小説家になった今、私の書くものの大半は、元をたどればAとのつき合いから生まれたものだ。Aがいなければ、私は小説家にはなっていなかっただろうし、現実の深淵や彼岸を考えることもなかっただろう。
恩義のあるAに、勝手な期待を抱き、卑劣な空想を弄んだことが、今も悔やまれる。
( 了 )